日本語学校で教えているとノートにメモをとる習慣を持っていない学生をよく目にします。しかし決してさぼっているわけではなく「ここは大切なところだからメモをしてね」と声掛けをするとはっとして一生懸命書き始めることがほとんどです。
日本国内の学校や補習校では教師がまとまった内容を板書して生徒はノートをとるのが主流ですが、国外の学校でノートはどんな役割を果たすのでしょうか。
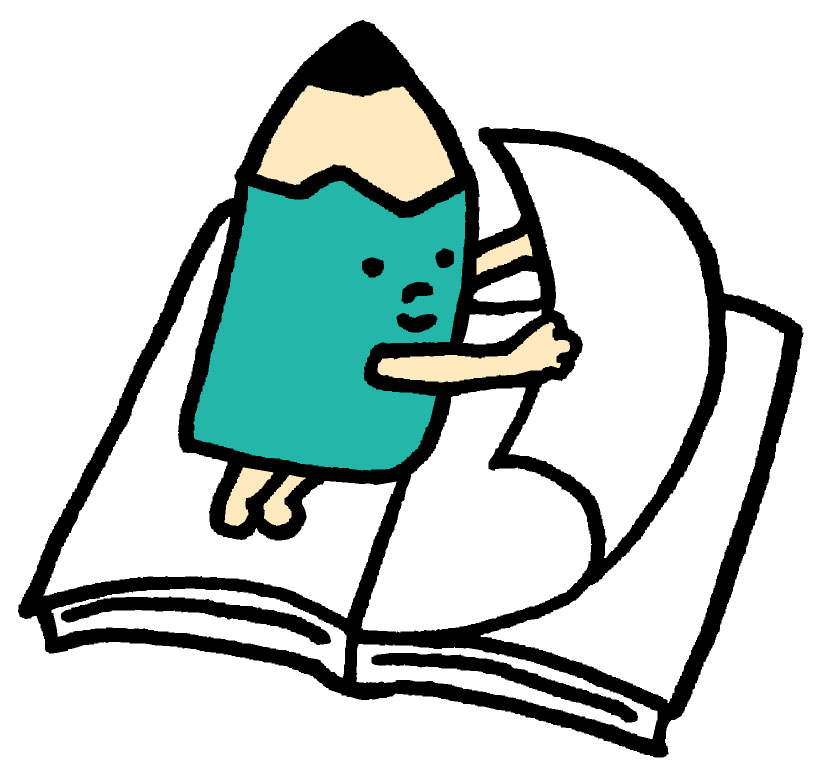
今日は日本語学習におけるノートテイキングのメリットを考えます。
①正確な書き取りをする習慣を得る
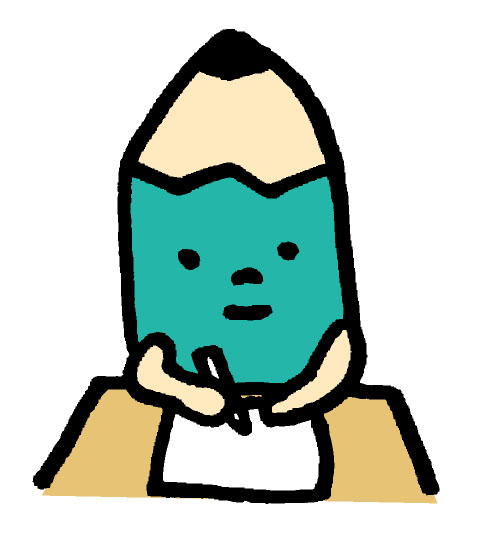
日本語は表意文字といって文字が音を表すアルファベットなどとは異なりそれ自体に意味を持っています。表記に正確性が問われるため、まずは習慣的に文字を正確に書きとる訓練が必要です。学習の際には必ずえんぴつ、消しゴムを使い、間違えたときには消して書きなおす、という習慣がノンネイティヴにとっては一つのステップになることもわかりました。
また、書くときにノートや体ををまっすぐにして書くという習慣も場合によっては身につける必要があります。生徒さんによっては紙をななめにして手を巻き込むような形で書きとるため、文字が「くせ字」となって誤って覚えているケースもありました。特定の言語の国でこういった特徴を持った書き方をする傾向が見られますがアルファベット言語の国の学生でも同じケースを見たので母語の影響とも限りません。
一見当たり前に思えますが日本語を書くときはえんぴつ、消しゴムを使うこと、
体と紙をまっすぐにして正確な字を書くこともまた学習のワンステップです。
②縦書きに慣れる
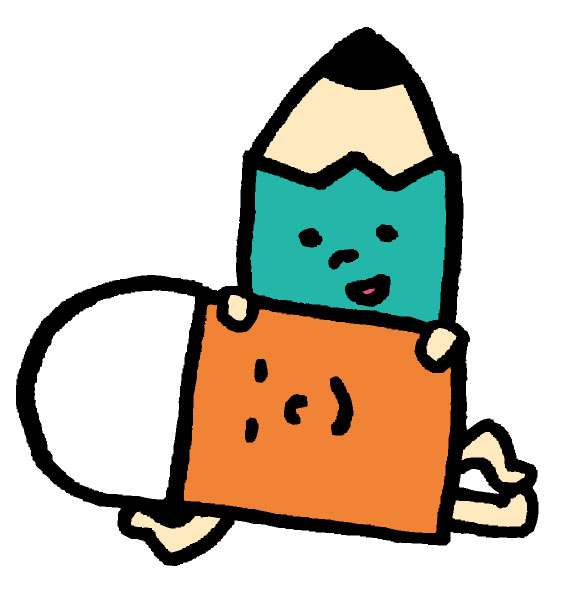
音読練習の記事でも紹介しましたが、横書きで書かれる文字を母語に持つ人にとっては縦書きでの書き取りが大きなステップとなります。一度留学生たちがはがきを書く練習をしたときの様子を見ましたが、文字と文字の区切りがわからず漢字が部首で分かれて改行されていた、などということもありました。
横書きの文章を左から右へ目を動かして下に向かって書き進めることから
縦書きの文章を上から下へ目を動かし、そして右から左へと、更に手を上下に動かしながら書きとるという行為は習慣となるまでは継続した練習が必要です。
もしお子さんが作文などの宿題への取り組みに気が進まない場合はこういった表記のルールの違いに戸惑いが見られるのかもしれません。
③書き言葉に慣れる
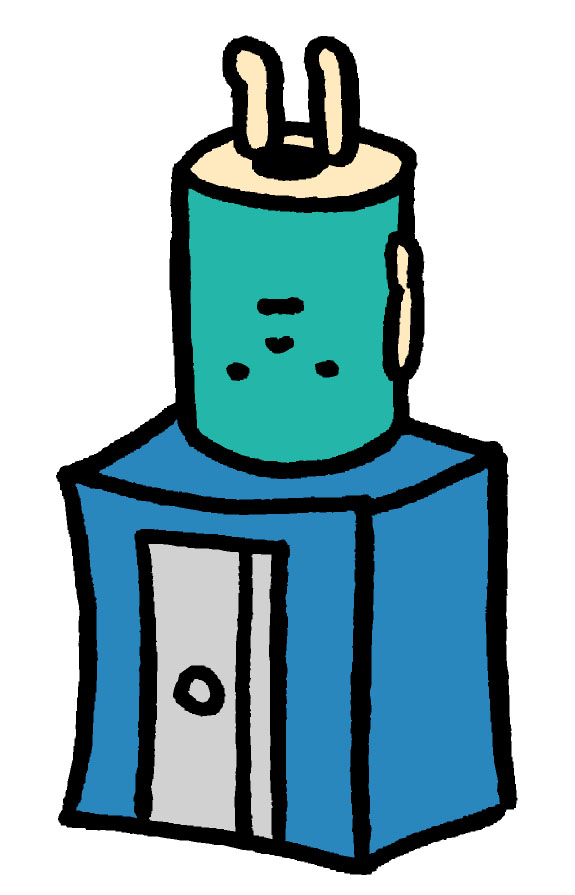
家庭の会話で日本語を使うだけでは身につかないもののひとつが書き言葉です。
会話では抜け落ちる助詞の「を」や「が」も日本語の大切な構成要素としてノートに書きとることで意識を向けたいところです。
また口語表現では使えても作文では使えない表現の学習の機会にもなります。
例)めちゃくちゃおいしい→とてもおいしい
そしてこちらは誤りではないのですが家庭で方言を使って話している場合もまた書き取りを通して教科書に用いられる日本語と家庭の言語との差異に触れる機会となります。
おわりに
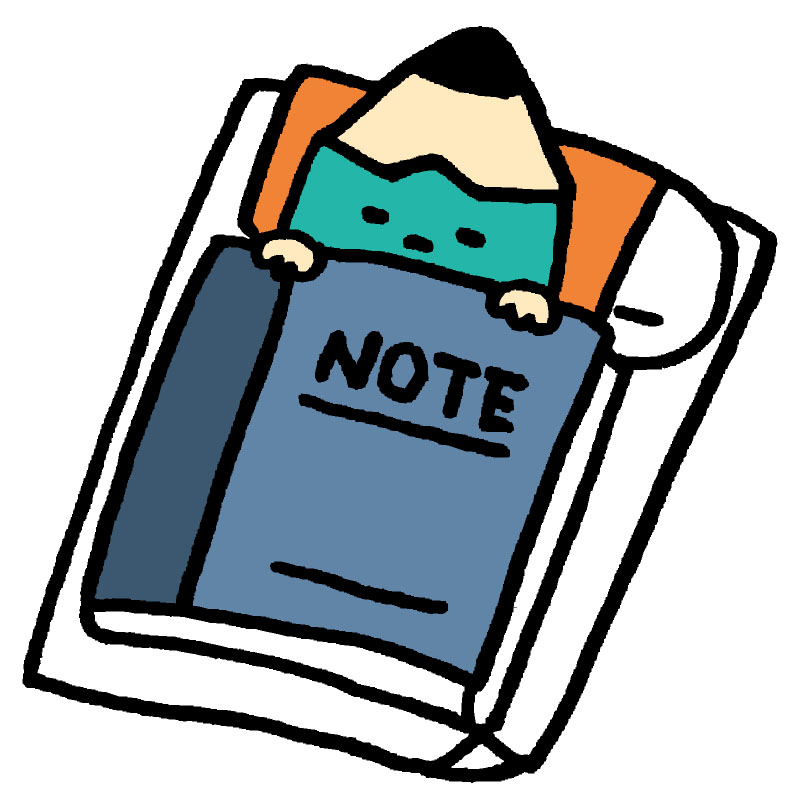
日本語でノートに書きとることはネイティヴにとっては当たり前のように感じられてもノンネイティヴにとっては様々なステップを経てできるようになることです。書くことは家庭の会話で日本語を使うだけでは補えない技能な上、継続した練習と習慣作りがとても大切になってきます。