海外在住で日本語学習に励むご家庭ではみなさんとても精力的に読み聞かせに取り組まれている様子が伺えます。日本語での読書習慣があれば教科書の音読や精読への移行もスムーズです。今日は日本語教師が考える読み聞かせのメリットについてお伝えいたします。

①日本語を聞いて理解する力が育つ
英語をはじめアルファベット言語の多くは日本語とは異なる文法構造を持っています。読み聞かせを通じてSOV型(主語・目的語・動詞)という日本語の文法構造の音声やまとまった話を聞きとり必要な情報を得る練習の機会作りができます。会話では抜けやすい助詞の「を」や「が」も書き言葉を読んで聞かせることによって文の構成要素としての意識を育てていきたいところです。

②語彙の拡張
日本語の本の中では家庭での会話では使わない語彙がたくさん使われています。
特に日本の昔話では「大判小判」や「機織り」、「糸つむぎ」など文化的、歴史的背景を持つ言葉がたくさん出てきます。本を通して触れなければ知る機会のない言葉の数々をぜひ読み聞かせを通じて知り、語彙を広げ、日本についての理解を深めてもらえればと思います。
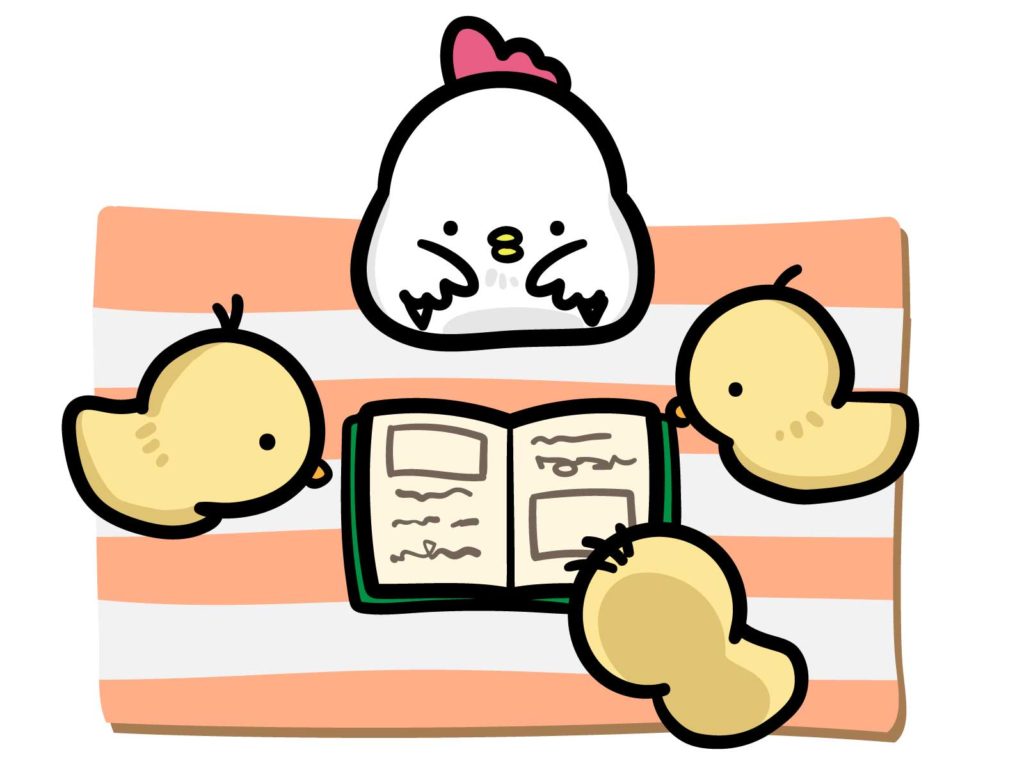
③慣用表現の学習
日本語学習者が「難しい」と考える表現のひとつが擬音語、擬態語です。
例)雨がザーザー降る / ぺちゃくちゃおしゃべりする など様子や音を表す表現は学習者に説明しても「そんな風には聞こえない・思えない」などという声が上がり言葉として捉えにくいようです。感覚的に捉えにくいがため実際に日本語に存在しないような擬音語擬態語をオリジナルで作って話している人も多く見かけます。
ノンネイティヴにとって聞いて実際にはそのように思えなくても慣用的に使われているのが擬音語、擬態語です。子供の本には擬音語・擬態語がたくさん出てきますので読み聞かせを通じて表現のバリエーションを知るいい機会作りができます。
また「道草を食う」(実際に道端の草は食べません)、「油を売る」(油も売りません)などその表現自体が特定の意味を持つ慣用句も読み聞かせを通して使われる状況を想像することができます。
余談ですが日本語学校で一度生徒さんたちに各国の動物の鳴き声(擬声語)について質問したことがあります。日本語ではにわとりの鳴き声は「コケコッコー」ですが、国によっては大きく異なり「ココココ」や「キッキリキー」など生徒さん同士でお互いに驚くような表現もありました。ちなみに「キッキリキー」はイタリアです!
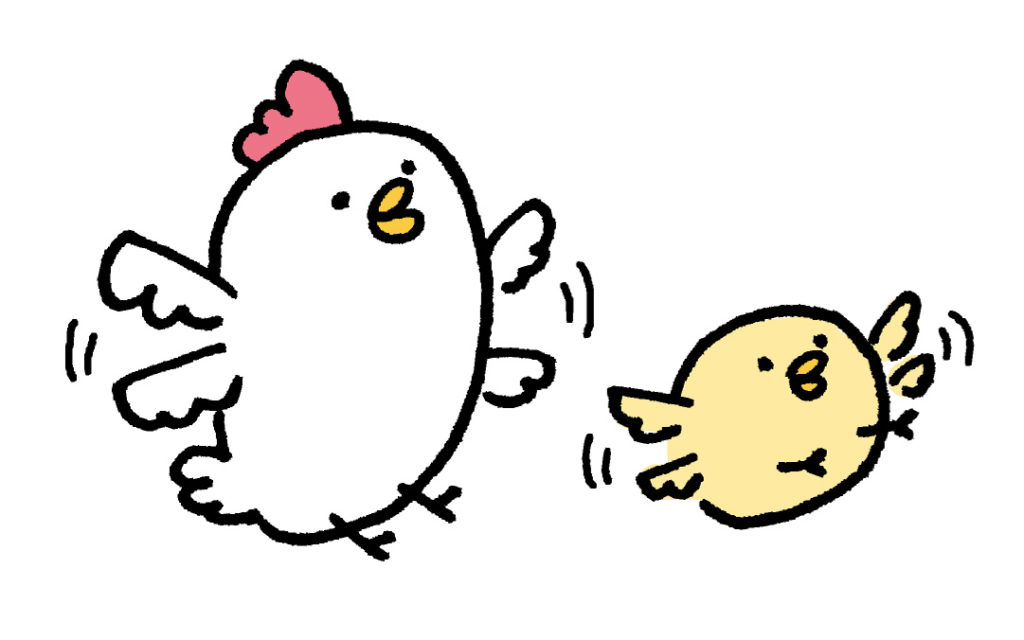
読み聞かせは家庭で気軽に取り組める日本語学習のひとつです。実際にお子さんたちは読み聞かせが好きな子が多く、日本語ネイティヴのご家族との触れあいのいい機会にもなっているようです。
今後も読み聞かせについていろいろご紹介してみたいと思います。